
人生を変えられた本はなにか? と聞かれたら、わたしは、高校生のときに読んだ、坂口安吾の「堕落論」だと迷いなく答えます。
(えっ、というか、青空文庫ってボランティアなのですね?? 知らなかった……! 著作権保護期間の終わった作品、みんな青空文庫さんで電子で読めるのがありがたいですねえええ)
それまでの(坂口安吾をよむまでの)わたしは、わりと「いろいろあるけど最後はハッピーエンド」とか、「なんだかんだ、がんばってたらなんとかなるよねー」といった、どちらかといえばご都合主義な文脈のストーリーやメッセージに心を支えられて生きてきていたところがあったので、
「人は正しく堕ちる道を堕ちきることが必要」
「堕ちる道を堕ちきることによって、自分自身を発見し、救わなければならない。」
と、安吾先生にはっきりと言い切られて、高校生のころのわたしは、「え、まじで……?!」「なんてロックンロールなんだ……!」と、がつーん! と頭を殴られたような気がしたものです。ほんとに。
ただ「堕落論」ですが、なんというか、
これをなんの前提知識もなく、いきなりぱっと読んでも「ほう……(どういうことなんだ…?)」としか思えなかったと思うんですね。少なくとも、当時高校生だったわたしには。
おそらく堕落論(が収録されている文庫本)を手に取ったきっかけは、高校の現代文の教科書にでてきた「文学のふるさと」の影響が大きかったと思われます。
生存の孤独とか、我々のふるさとというものは、このようにむごたらしく、救いのないものでありましょうか。私は、いかにも、そのように、むごたらしく、救いのないものだと思います。この暗黒の孤独には、どうしても救いがない。我々の現身(うつしみ)は、道に迷えば、救いの家を予期して歩くことができる。けれども、この孤独は、いつも曠野を迷うだけで、救いの家を予期すらもできない。そうして、最後に、むごたらしいこと、救いがないということ、それだけが、唯一の救いなのであります。モラルがないということ自体がモラルであると同じように、救いがないということ自体が救いであります。
私は文学のふるさと、或あるいは人間のふるさとを、ここに見ます。文学はここから始まる――私は、そうも思います。
坂口安吾のエッセイ全般に言えることですが
「規則によって律することや枠組みで制御したりすること、またそれによって救われようとすることは、一時的な措置にすぎない」
「人間は圧倒的に孤独であり、そのことを心から理解することが唯一の救いである」
といったテーマが流れているように思います。孤独なのがあたりまえ。欠けているのがあたりまえ。満たされないということが基本で、そこからどうするか? みたいな。
安吾先生の近くに「ああー私ってダメだなあ」なんて嘆いている人がいたら「いや、それがふつうだから。あなただけじゃなくて、そもそも人間ってダメなのがふつうだから。人間も人生もダメなのは当たり前なんだけど、大事なのはダメなのがわかったうえでどうするか? ってところだからね」
とか言いそうです。笑(想像ですが)
そういう突き放したスタンスに、心があらわれるような、勇気づけられるような感動をおぼえたものでした。
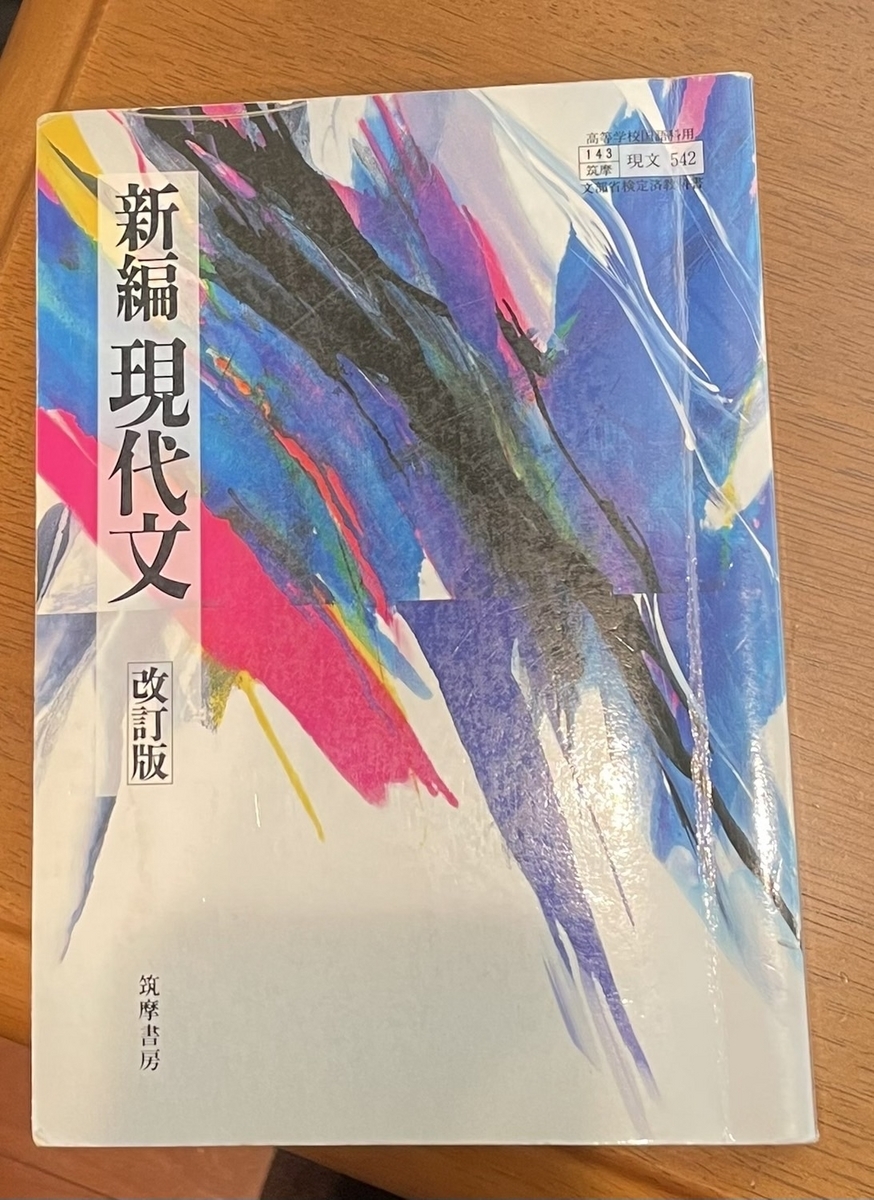
高校時代の国語、特に現代文の授業って、わたしにとってラッキーボーナスタイム(やったー、授業中に本読めるし、しかも先生が丁寧に解説してくれる!)でしかなく、趣の深い時間だったなあと思います。
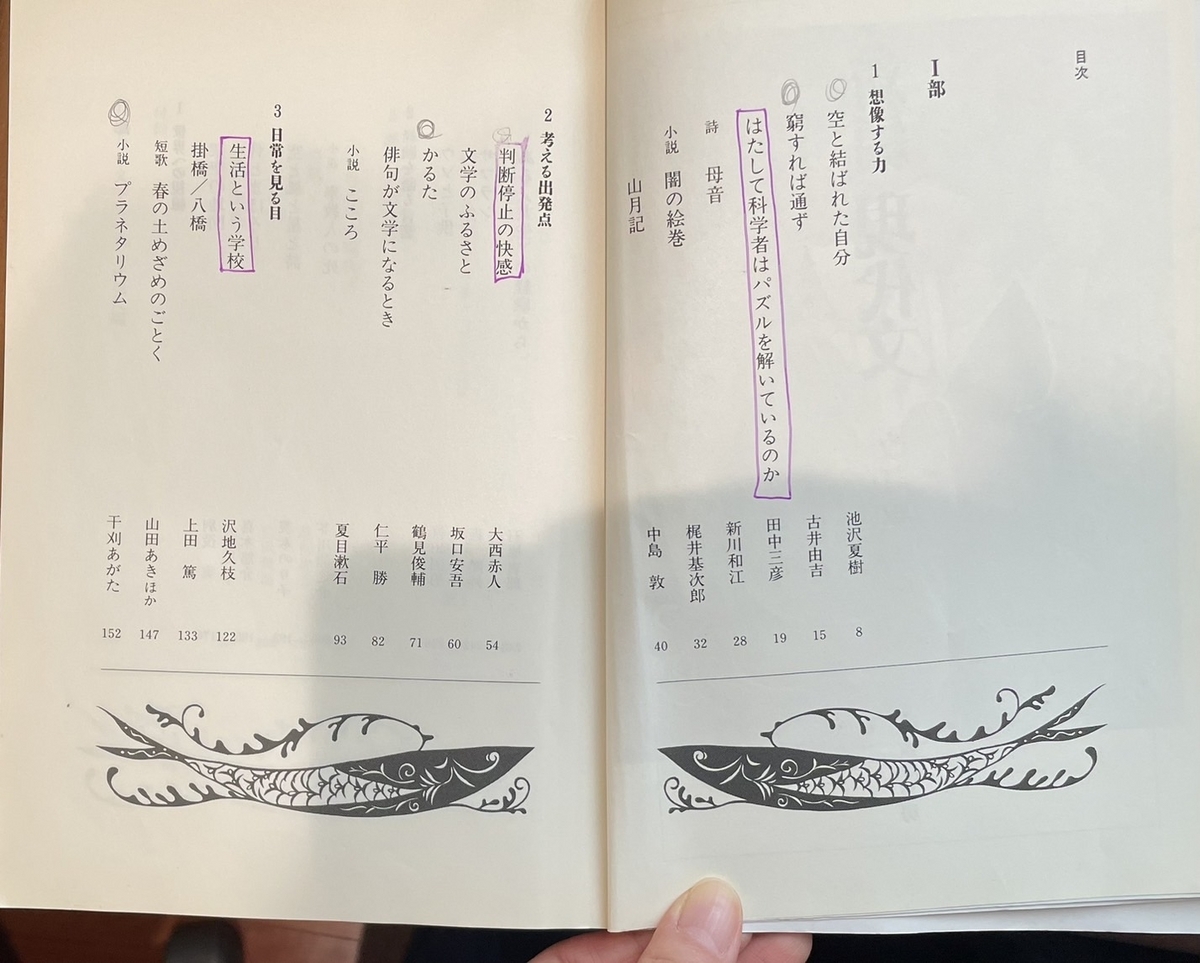
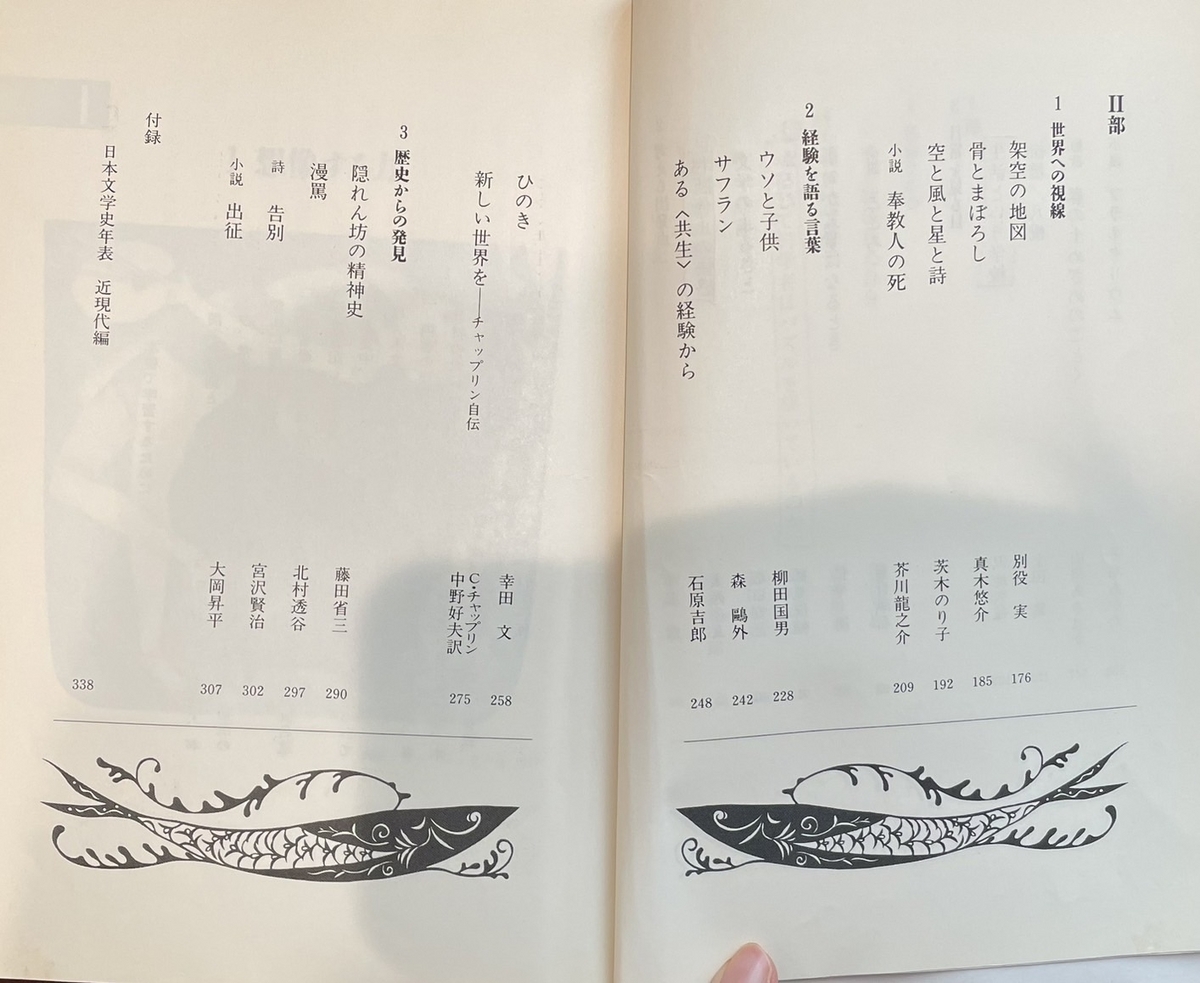
名作アンソロジー(文学世界への誘い)じゃんか……現代文の教科書おそるべしです
この教科書は高2のときのもので、他のはみんなどこか行ってしまったのですが、手元においておけばよかったなあ